[vc_row][vc_column][vc_column_text]
2015y FORD MUSTANG Eco Boost
SOUL OF FORD NEVER ENDS
果てしなく続く熱きフォード魂
レースカー専門メーカー「RTR」のボディキットを装着
2019年モデルに限定で、レースカー専門メーカーであるRTRとコラボしたハイパフォーマンスモデルのマスタングが登場し話題となるが、紹介するマスタング・エコブーストは、そのRTRボディキットを装着し、オールインポートが日本総代理店となるCOBBチューンを施した、本家にも劣らないスペシャルマスタングだ。
限定モデルに負けないスペックを誇る
フォードは様々なチューニングブランドを中心にコラボレーションモデルを販売するが、特に主力となるマスタングはその数が多い。2019年モデルでも、ドリフトワールドチャンピオンのバン・ギットンJr率いるRTRビークルズとコラボレーションした「シリーズ1・マスタング RTR」を限定500台で販売する。エンジンのチューンこそないが、調整式のフォード・パフォーマンス製スタビライザー、マグネライド・サスペンション、19インチ専用ホイールに変更されるなど、足回りを強化した内容だ。
今回オールインポートが完成させたのは、そのRTRビークルズから発売しているRTRマスタングボディキットを身にまとい、同ショップが日本総代理店として扱うエコブースト用チューニングキットCOBBチューンを組み合わせたモデルだ。[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
エコブーストは非力という概念を覆す、COBBチューンの破壊力

65hp向上を実現するCOBBチューン
ベースとなるモデルは15年型マスタング・エコブースト。ここにRTRのボディキットであるLEDアクセントフロントグリル(アッパー&ロー)、フロントスポイラー・SPEC2、サイドエクステンション、リアスカートエクステンション、リアスポイラーを装着し、ホイールは同じくRTRのフローフォーム軽量モデルの20インチ(テック7・チャコールグレー)、タイヤはニットーのウルトラパフォーマンスタイヤNT555G2を組み合わせる。
もちろんこれだけでも注目に値するスタイルではあるが、エコブースト用チューニングキットCOBBチューンの、ハイスペックタイプであるステージ3を施し、COBBパフォーマンスコイルも追加する。COBBチューンはECUチューンデバイス「アクセスポートV3」をセットするステージ1、インタークーラー&専用大径インテークを追加するステージ2、エギゾーズトが加わるステージ3のメニューがあり、フルチューンのステージ3では65hpアップになるという。ノーマルでは非力な感じがする排気音もかなり刺激的な音量となり、走りへのワクワク感が溢れ出る。

COBBチューンだけでは、ノーマルとの見た目の違いが余り感じられないが、RTRのキットを身にまとうことで、誰がどう見ても快速仕様なのが伝わってくる。





装着するRTRのボディキットは、LEDアクセントフロントグリル(アッパー&ロー)、フロントスポイラー・SPEC2、サイドエクステンション、リアスカートエクステンション、リアスポイラー。ホイールはフローフォーム軽量モデルのRTR・テック7・20インチ(F20×9.5J・R20x10.5J/チャコールグレー)、タイヤはニットー・NT555G2(F255/35・ R275/30)を組み合わせる。
エコブーストチューニングキットCOBBチューンは3段階のチューニングメニュー



チューニングレベルに合わせて、ステージ1、ステージ2、ステージ3という三段階のチューニングのセッティングメニューがあるCOBBチューニング。ステージ1はECUチューンデバイス・アクセスポートV3、ステージ2はステージ1+インタークーラー&専用大径インテーク、ステージ3はステージ1&2+エギゾーズトがセットとなる。今回のモデルはステージ3に加えて、COBBパフォーマンスコイルを追加してチューニングが施されている。[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Thanks/オールインポート
TEL:048-959-9419
URL:http://www.allimport.jp[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Photo/古閑章郎
Text/相馬一丈[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]アメ車マガジン 2019年 6月号掲載[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]



































































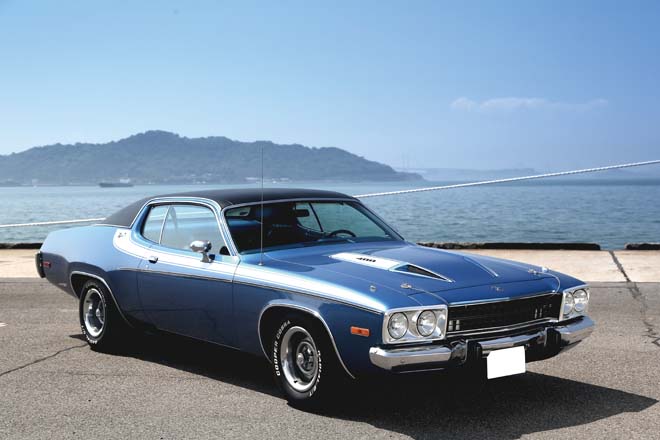



 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Text & Photos|アメ車MAGAZINE[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Text & Photos|アメ車MAGAZINE[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]



































 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Thanks:WINGAUTO(シボレー名岐)
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Thanks:WINGAUTO(シボレー名岐)



















