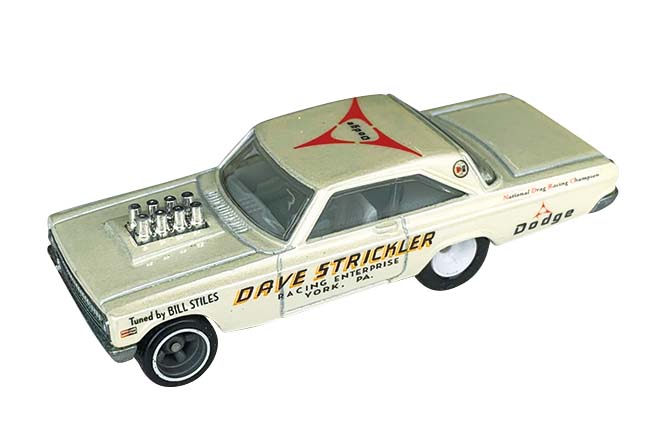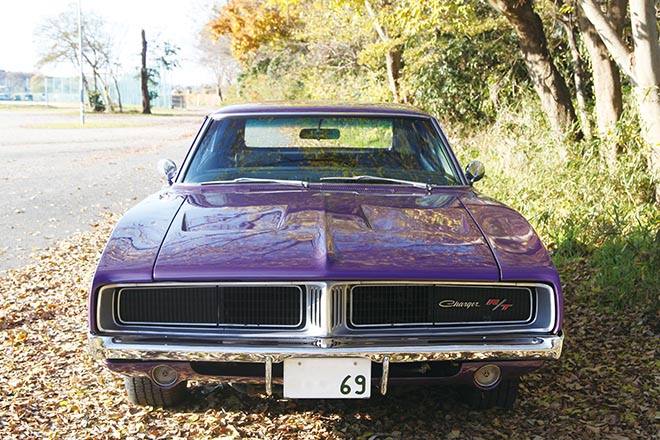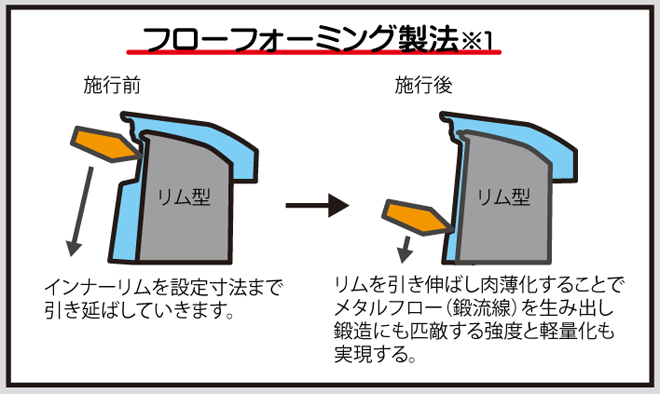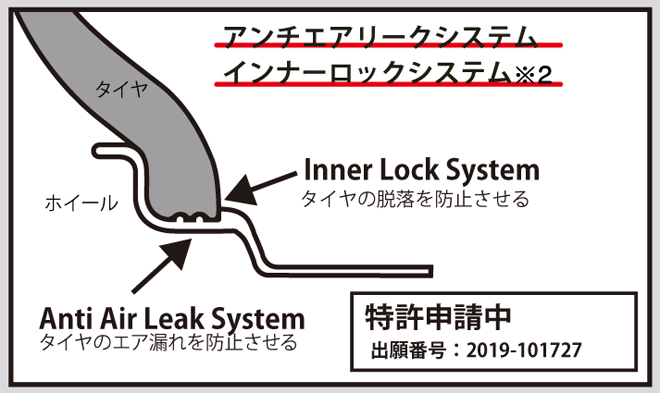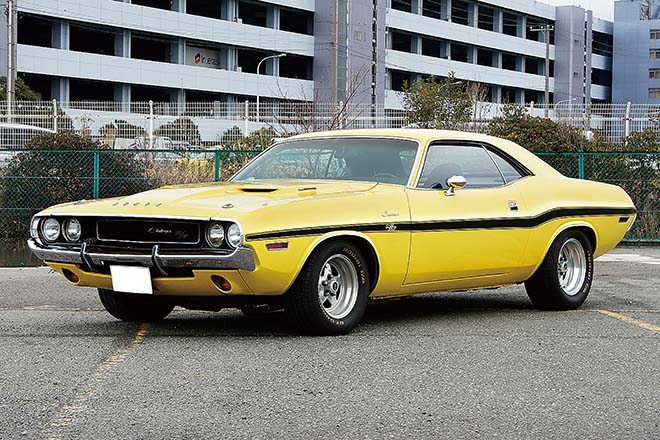[vc_row][vc_column][vc_column_text]
LATEST JEEP JL WRANGLER CUSTOMS in SEMA SHOW 2018
LAS VEGAS CONVENTION CENTER
LAS VEGAS,NEVADA OCT 30 – NOV 2,2018
個性的なエッジの効いたデザインのパーツをリリース中

直線基調のデザインを採用するBR4×4のオリジナルパーツ。JKと比べるとJLは丸みを帯びた印象を受けるが、BR4×4のパーツを装着すると非常にシャープな印象を受ける。スイング式のスペアタイヤブラケットに交換し、その隙間に燃料や水などが入れられるROTOPAXを装着可能としている。
ランプメーカーもJLに注目新たなスタイルが予感される

様々なLEDのランプをリリースするDIODEDYNAMICSでは、フロントバンパーやボンネットの上にLEDライトバーを装着したJLを展示。フロント周りは今や珍しくないが、ルーフの後端にもLEDを装着するのは斬新と言える。
ドイツ企業もSEMAに注目欧州でもJEEP人気は増加中

JEEPとラム専用のホイールを展開するBAWARRIONは、純正のタイヤ空気圧センサーにも対応したホイールを展示。また、開発中のオーバーフェンダーをノーマルと比較。それにフロントマスクはCJフェイスへコンバート。
機能性を最大限に重視したラックやステップに注目

KARGO MASTERのブースには、オリジナルのルーフラックや折りたたみ式のステップを装着。フロントウインドーを取り囲むロールケージはラックと一体で、しかもここに立てる形状を採用。使いやすさを最優先に作られている。
往年のCJ7を彷彿とさせるデカールが非常に象徴的

JCR OFFROADのブースには、ショートのJLを展示。足回りはテラフレックスにファルコンショックを組み合わせる。ゴールデンバンディットという愛称が与えられており、それにちなみ各部の色をブラック×ゴールドで統一する。
オリジナルのパイプドアやランプステーをリリース

MOTORCITYのブースには、パイプドアにアレンジしたルビコンを展示。オリジナルのフラットフェンダーかと思いきや、実は純正フェンダーのブラックの部分を取り外しただけ。これだけでも、より大きなタイヤが装着可能だ。
バンパー類を金属製に交換ヘビーデューティさを追求

オリジナルのバンパーやサイドシルガードなどをリリースするROCK’SのJLラングラー。JKラングラーで確立されたスタイルがそのままJLにも注入されており、JLカスタムの基本スタイルになると言えるだろう。
乗車定員を損なうことなく快適な車中泊が楽しめる


ボルトオンで様々なアイテムをリリースするCLIFFRIDEでは、2種類のキャンパー仕様のJLを展示。巨大なシェルを装着したFE4と呼ばれるモデルは、4人の乗車定員を確保したまま4人が快適に就寝できるスペースを確保。また、ESCAPE365と呼ばれるモデルは、いわゆるポップアップ式のテント。快適性はFE4には敵わないが、手軽にキャンピングライフが楽しめる。共に、ノーマルよりもワイドなフェンダーを装備し、安定性も追求する。
日本でも人気が急上昇中! ラインアップの拡充に期待

敢えてアルミ無垢のまま仕上げられているのが、言わば一つの個性となっているGENLIGHTのパーツ。サスペンションはROCK KRAWLERで、Aピラー部分にはRIGIDのLEDランプを装備。ロッカーガードやタイヤキャリアなど、JKに用意されていたアイテムが、続々とJLにも発売予定だ。
ルーフ一体式のシェルで車両のシルエットを変更


JLのルーフが簡単に外せることに着目し、アメリカンファストバックでは、様々なスタイルを提案。これまでトレックトップというスタイルで、幌では他社から発売されていたが、ハードタイプのファストバックは世界初と言える。また、ディスカバリー風のルーフを採用した仕様もなかなか個性的で、クォーター部分には窓も設けられ、居住性もアップ。ちなみにこの車両にはイートン製のスーパーチャージャーが装着されており、そのパフォーマンスもなかなかだ。
グリルやヘッドライトに白のアクセントを加える

ロックスライドエンジニアリングのJLは、鮮やかなグリーンと対照的な白いシートが印象的。いわゆるヘビーデューティなバンパーを装着しているが、非常に美しい光沢が特徴でオフロードで傷つけるのがもったいないと思えるほど。
機能と実用性を備えたJLカスタムの見本的仕様

スチールクラフトのJLには、同社のウインチバンパーを装着。定番になりつつあるパイプドアに変更。サイドステップは非常に大型のもので乗降性を向上するが、ハードなオフロード走行にもしっかりと耐えられる作りとなっている。
グラディエーター公式発表より先にトラックモデルが登場

LAショーでグラディエーターが発表されたが、それより先にSEMAの会場では何台かトラックにコンバージョンした仕様が登場。ボディガードブースに展示されていたのもその1つで、なかなかの完成度を誇っていた。全身チッピング塗装を施しており、非常に無骨な雰囲気を漂わせていた。
コントロールアームも変更してJEEPの力を最大限引き出す

MAXTRACサスペンションのブースに展示されていたJLは、ファルケンの38インチタイヤを装着。バギー風の背面タイヤキャリアが、走りのポテンシャルの高さを予感させてくれる。前後のコントロールアームはピロボールになっており、しなやかな動きを実現。フェンダーの下を外すのが流行るかも。
またまたフルチッピング日本でも流行るか?

DV8 OFF ROADのブースには、自社製品をフルに盛り込んだJLを展示。非常にコンパクトなフェンダーやヘビーデューティな前後バンパーを装着。ホイールも同社のもので、38インチのRIDGEグラップラーを組み合わせる。
ビードリングとボディのマッチカラーはもはや定番

日本でも、高い知名度を確立しているラギッドリッジ。ショートのJLを展示し、オレンジのボディカラーとマッチさせたビードリングが美しい。クローリングバンパーから直射日光を遮るスクリーンまで、様々なアイテムを提案する。
まさにモンスターJEEP!エンジンをLS3に換装

JLにV8を載せたのは何台かいたが、シボレー・コルベットのLS3を載せてしまったのはこの1台だけ! ビルダーが言うには450hpを誇るとか。ニックネームのBRUISERは乱暴者という意味で、まさにその通り!
JKで培った独自のスタイルをまずはJLにも注入する

日本で圧倒的な人気を誇るポイズンスパイダーもJL用の新製品を一気にリリース。JKでラインアップしていたエクステリアからインナーフェンダーまでを同様にラインアップ。ポイズンスパイダー製品以外はチッピング塗装を実施。[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]PHOTO◆TAKEO ASAI
TEXT◆RYO SORANO[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]アメ車マガジン 2019年 3月号掲載[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]